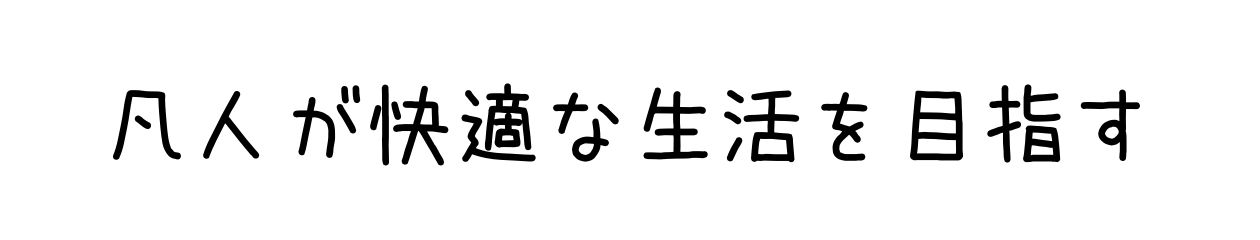そこそこ良い研究生活を送るための研究室の選び方について
1.研究テーマに興味があるか
2.自分がその研究室に入れそうか
3.教授との相性が良さそうか
4.教授の指導方針が良さそうか
5.研究室内からを不満を感じるか
6.研究室内の雰囲気が良さそうか
7.学会に行く機会がありそうか
8.コアタイム(休み)があるか
9.プライベートを重要視しているか
10.修士課程に進む割合が多いか
11.研究室の実績が充実しているか(論文や研究費など)
これらに着目するといいかも。
こんなテーマについて話していく。
研究室選びに興味のある人は読んでみて。
自己紹介
社会人2年目です。
電気電子を専攻していましたが、正直そこまで興味無いです
ブログ運営が趣味で、自分の体験をあれこれ書いています
目次
そこそこ良い研究室の選び方

「将来、特に研究職に就きたいわけでもなく、なんとなく大学院生までは大学にいよう」
このように考えている人向けに研究室の決め方について話していく。
僕もそうだったので、気持ちはよくわかる。
1.研究テーマに興味があるか
2.自分がその研究室に入れそうか
3.教授との相性が良さそうか
4.教授の指導方針が良さそうか
5.研究室内からを不満を感じるか
6.研究室内の雰囲気が良さそうか
7.学会に行く機会がありそうか
8.コアタイム(休み)があるか
9.プライベートを重要視しているか
10.修士課程に進む割合が多いか
11.研究室の実績が充実しているか(論文や研究費など)
これらの指標があると思っているので、簡単に補足させてください。
1.研究テーマに興味があるか
研究テーマの選定はそこそこ重要。
まったく興味のない研究を継続することは地獄、、
そもそも学科の分野自体にそこまで興味のない人もいるかもしれないが、消去法でもそこそこ興味のある研究テーマがある研究室に所属した方がいいですよ、、
正直、おもしろさなんて始めてみないとわからないので、なんとなく興味あるな程度でも良いと思う。
僕の場合はなんとなく将来性がありそうな「電子回路」系の研究室を選びました。
結局、特別面白かったわけではなかったが、
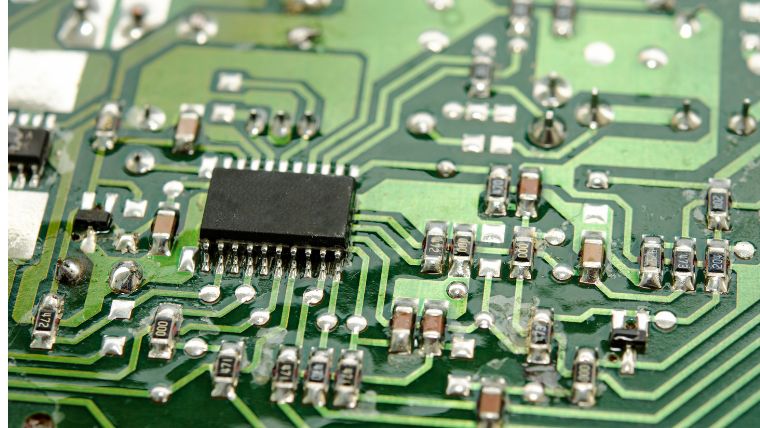
2.自分がその研究室に入れそうか
研究室に所属できる実績やGPAを持ってることも重要。
第1希望で落ちて第14希望になるなんて馬鹿げたことも僕の大学ではあった、、
大学内で研究室を選ぶなら、研究室の人気度と自分のGPAを基に決めた方がいいときもありそう。
場合によっては学部生で行きたい研究室は諦めて、第1希望と似たような研究室に行き、大学院から希望の研究室に行くこともアリ。
ちゃんとアピールして院試で良い結果を出せれば、修士からならだいたいどこの研究室も行けますよ(少なくとも僕の大学は)。
重要なことは絶対に行きたくない研究室に配属にならないように動くこと。
ここ超大事!!

3.教授との相性が良さそうか
研究室に配属後は、進捗報告会(ゼミ)・研究室内のルール・研究の相談・予稿や論文の修正などなどあらゆることに教授が関与する。
教授と相性悪かったらかなり地獄
個人的にオススメする教授の特徴は厳しいけど、研究相談の時間は確保してくれる人。
社会人になってから、教授からの指摘が割と仕事に活きているんですよね。
プレゼンの仕方や研究の進め方など。
研究室訪問などで教授に関する情報を仕入れてみてください。
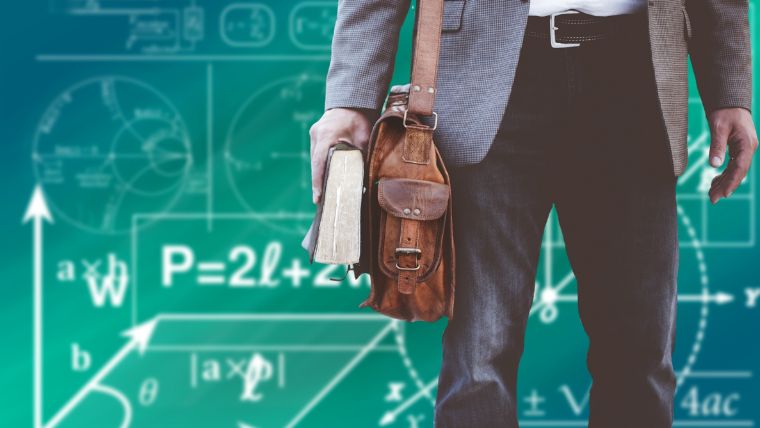
4.教授の指導方針が良さそうか
教授の指導方針が良ければ、自身のスキル向上となり、研究も進む。
研究の進め方、アドバイス、プレゼンのコツ、文章の書き方など、研究以外のこともフォローしてくれる教授は普通に良い!
進捗報告のネチネチとした指摘も実際ありがたい情報だったりするんだよねー
前述したが、
ホントに社会人になってから、研究室での教えが活きているんですよね。
教授の特徴は研究室訪問で間違いなく仕入れるべき情報。
ちなみに、教授からの指導がない研究生活について良し悪しあると思っています。そんな話をこちらで話しています。よかったら読んでみてください。
教授からの指導のない研究室は辛いのか?【むしろプラスなのでは?】
5.研究室内から不満を感じるか
地獄のブラック研究室からはどことなく、研究室内から不満のような負のオーラが漂っているもの。(これホントに)
研究室訪問の際に、研究室の人と話したりしてみて研究室の不満を嗅ぎ取ることをオススメする。
違和感を覚えたら危ないかもね。

6.研究室内の雰囲気が良さそうか
居心地の良い研究室は雰囲気が良い。
教授とも距離が近すぎず、遠すぎず。
そして、わからないことも先輩に聞けるような雰囲気だと最高。
僕の場合は、女性もいたのでなんとなく雰囲気の良さを感じていた。
#女性がいるだけ最高
実際入った後も雰囲気は良かった。
(なかなか馴染めなかったけど)
雰囲気は研究室訪問で感じ取ってください。

7.学会に行く機会がありそうか
学会発表は程よくできるといいよねー
まあ、学会発表あまり多いと、準備のために研究室に閉じこもることになって地獄ツアーのような研究生活になるが.、、
しかし、学会発表が少なすぎると「学会」という貴重な経験もできないし、無料国内・海外旅行のチャンスもなくなってしまう。
修了してから思いますが、
英語で自分の研究発表する経験は間違いなく、良い経験だった。
研究室によって学会に行く頻度が違うと思うので要チェック。
研究テーマによってはなかなかイケないところもあるんですよねー
(学会発表で死んだ話→英語力なし&研究成果弱いヘボ大学院生が海外で学会発表をした話)
8.コアタイムがあるか
人生の中で研究という貴重な体験は大学生しかできない可能生がある。
それでも休みは超重要。
むしろ、休みが1番重要かもしれない。
研究に縛られない自由な時間を大事にしてください。
ちなみに、大人になってもコミュ力や大事になってくるので、自由な時間を使って色んな人と飲み会か何かして、話してみてもいいかも。
僕の大学院生生活は6割研究、4割他事だったが、めちゃくちゃ楽しかった。
コアタイムと休み具合は確認しておいた方がいいですよ。
少し余談になりますが、下記の記事ではホワイトな研究室の特徴についてまとめています。よかったら読んでみてください。

9.プライベートを重要視しているか
教授がプライベートを重要視しているかはかなり重要。
ここを重要視しているなら、
計画通り研究しているパフォーマンスを見せれば、就活関連、遊び関連で研究室にいなくても特に文句は言われません。
プライベートガン無視でインターンに行くこともハードルが高いような研究室は面倒くさいですよね。
絶対嫌!

10.修士課程に進む割合が多いか
修士課程に進む学生が多いだけで、
研究体制が整っていること、真面目な学生が多いことなどの証拠になる。
質問できる先輩もいるということで、人の多さは研究面において良さしかない。
もちろん、人間関係の面倒さは増えるかもしれませんが、無理に仲良くなる必要はないので、そこまで気にしなくていいと思いますよ
だいたいなんとかなる。
11.研究室の実績が充実しているか(論文や研究費など)
研究室論文投稿や研究費などの充実さも1つの指標になると思う。
まあ論文投稿などは博士課程に進まない限りそこまで重要ではない。
論文投稿の義務がないので。
研究費は重要ですが、
そこそこ研究体制がしっかりしていれば、修士学生ごときでは困ることはないとは思う。
とりあえず、ここまで11個くらい研究室を選ぶときの指標的なものを書いてみたが、情報は研究室訪問で仕入れてみてください。
ちなみに質問事項などの注意点をザックリ下記の記事で紹介しています。よかったら読んでみてください。
研究室訪問するならとりあえず聞いとけ質問についてまとめた【実体験】
まとめ
この記事では、「将来、特に研究職に就きたいわけでもなく、なんとなく大学院生までは大学にいよう」
こんな考えの人に向けて研究室の選び方について紹介しました。
1.研究テーマに興味があるか
2.自分がその研究室に入れそうか
3.教授との相性が良さそうか
4.教授の指導方針が良さそうか
5.研究室内からを不満を感じるか
6.研究室内の雰囲気が良さそうか
7.学会に行く機会がありそうか
8.コアタイム(休み)があるか
9.プライベートを重要視しているか
10.修士課程に進む割合が多いか
11.研究室の実績が充実しているか(論文や研究費など)
そこそこ研究がしっかりできて、指導してもらえる研究室をオススメします。
以上。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
下記の記事では元駅弁大学院生の大学院生活をまとめています。
よかったら読んでみてください。