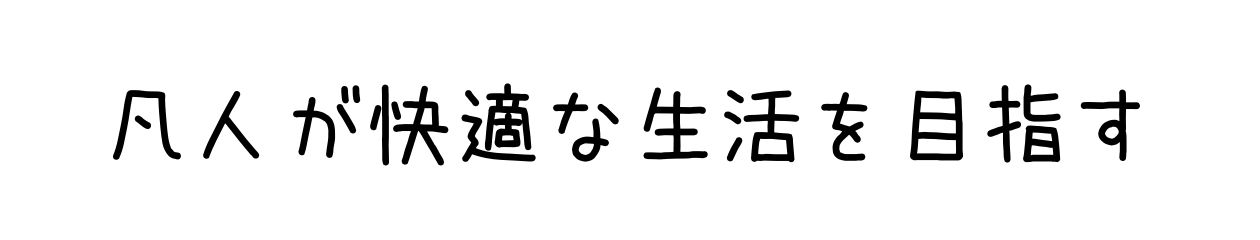カメさんを冬眠させるときの注意点
・飼育ケースは狭くする
・水をたくさん入れる
・定期的にカメの様子を確認する
・光が当たらないようにする
・水温が下がりすぎないようにする
・うるさくない場所で冬眠させる
こんなテーマについて話していく。
カメさんの冬眠について参考にしたい人は読んでみて。
自己紹介
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)を20年間飼育している。
これまで様々な飼い方を試してきましたが、今も元気に生きています。
目次
カメの冬眠の流れ

まず、冬眠までの流れについて。
僕の場合、毎年ほぼ同じ流れでカメさんを冬眠させている。
①気温が下がるとカメが餌を食べなくなる(12月上旬)
②冬眠用の飼育ケースに移す
③気温が上がるとカメが動き出す(3月下旬)
まず、11月頃気温が20度下回ってくると、カメさんの食べる餌の量が減ってくるんですね。
だいたい、12月の上旬にはまったく餌を食べなくなるかなー
そうなったら冬眠用の飼育ケースに切り替え。
(冬眠用の飼育ケースの特徴はこの次に説明する)
冬眠用の飼育ケースに移すと、自然とカメさんは冬眠を始めます。
だいたい3月くらいの気温が上がり始めたころに動き始めるかな。
動き始めてからは元の飼育ケースに戻して定期的に餌をあげてみて、しっかり食べ始めたら冬眠の終わり。
これが毎年のルーティーン。
カメの冬眠の注意点
そんなルーティーン化している冬眠についても、やはりいくつか注意点はある。
・飼育ケースは狭くする
・水をたくさん入れる
・定期的にカメの様子を確認する
・光が当たらないようにする
・水温が下がりすぎないようにする
・うるさくない場所で冬眠させる
それぞれ簡単に説明させてください。
注意点① 飼育ケースは狭くする
まず、飼育ケースはあまり大きくしない方がいい。
理由は2つ。
・狭い方がカメも落ち着くから
・光が当たらないようにしやすいから
まず、飼育ケースは狭くした方がいい。
実際、何度か広いケースで冬眠させようとしたが、カメがちょこちょこ動いてしまうんですね。
そこで無駄なエネルギーを使うことで、餌を食べていない冬眠中に死んでしまう可能生がある。
そこで、狭い飼育ケースに切り替えてみたところ、カメさんもあまり動かなくなり冬眠モードに入った。
そんなこんなで、飼育ケースは狭いものを使うといいと思っている。

注意点② 水をたくさん入れる
2つ目の注意点は、水をたくさん入れること。
水をたくさん入れた方がカメさんが落ち着いている気がする。
理由はよくわからないけど、、
自然界では落ち葉や土の中で冬眠しているかもしれないが、僕は水の中で冬眠させている。
水の中であれば定期的にカメの様子を確認することができるので、安心。
窒息死することも無さそうなので、心配はいらない。
(もちろんリクガメではなく水棲ガメに関する話ね)
注意点③ 定期的にカメの様子を確認する

3つ目の注意点は、定期的にカメの様子を確認すること。
冬眠中に病気になる可能性があるので。
カメさんは冬眠中でも病気になる可能性がある。
カメさんを触ってもまったく動かなかったり、浮いていると危険。
2週間に1度くらいは定期的にカメさんの様子を確認した方がいいよ。
ちなみに、カメさんは冬眠中ずっと寝ているわけではないみたい。
水温が低くなることで、活動が鈍くなって眠る時間が増えるだけ。
そのため、触れば何かしらの反応をして、また眠りにつく。
もちろん確認のしすぎは余計なエネルギーを使わせてしまうことになるので注意が必要。
注意点④ 光が当たらないようにする
4つ目の注意点は、光が当たらないようにすること。
カメさんが中途半端に起きてしまうから。
中途半端に起きた状態が続くことで、
餌を食べていないので、栄養補給ができないままエネルギーを使うことになるんですよね。
そうなると、カメが弱ってしまうので危険
光が当たらないように飼育ケースに布をかぶせる、リビングなどの常に電気がついている場所では冬眠させない、などの工夫が必要。
注意点⑤ 水温が下がりすぎないようにする

5つ目の注意点は、水温が下がりすぎないようにすること。
カメさんが凍死してしまう可能性があるから。
冬眠中は無敵モードでどんな気温にも耐えられるわけではない。
水温5度以下は危険。
とりあえず家の中の気温が5度以下にならなければ、基本的には水温も5度以下にならないと思われる。
逆に、温度の上がりすぎも中途半端な冬眠になってしまい、余計なエネルギーを使わせてしまうのでダメだからね。
温度が上がりすぎず、下がりすぎない場所で冬眠させましょう。
まあ、暖房のきいていない室内での冬眠が安パイ。
注意点⑥ うるさくない場所で冬眠させる
6つ目の注意点は、うるさくない場所で冬眠させること。
光同様にうるさいことで、カメさんが中途半端に起きてしまうから。
テレビの音などの生活音があまり聞こえない場所の冬眠をオススメする。
とにかくカメさんを気持よく寝かせる環境が重要。
冬眠をさせない方がいいカメの特徴

最後に、冬眠させない方がいいカメの特徴についてまとめる。
「カメの飼い方がよくわかる本」によると、このような特徴を持つカメは冬眠させない方がいいみたい。
・元々熱帯に生息している
参照:カメの飼い方がよくわかる本
・夏から冬眠するまで餌をたくさん食べていない
・弱っている
・生後2年以内
・健康状態が悪い
これらの特徴に当てはまらない水棲ガメなら基本的に冬眠でOKだと思うよ。
上記の条件に当てはまる場合は、冬眠させない飼育が必要になる。
詳しくはこちらの記事で:水棲ガメを冬眠させない飼育の解説【本・記事を参考】
まとめ
この記事では僕の経験を基に、カメさんの冬眠の注意点について話した。
・飼育ケースは狭くする
・水をたくさん入れる
・定期的にカメの様子を確認する
・光が当たらないようにする
・水温が下がりすぎないようにする
・うるさくない場所で冬眠させる
カメさんを冬眠させるときに、この記事が少しでも参考になれば嬉しい。
以上。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
下記の記事では、僕のカメさんの飼育方法をまとめています。
よかったら読んでみてください。