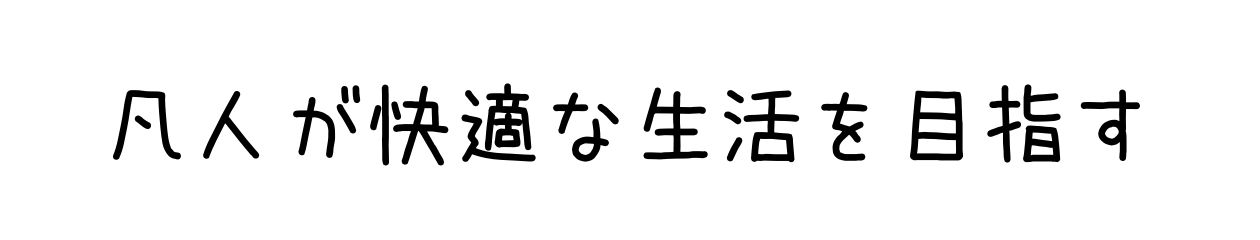「余計なモノを手放しきった少ない持ち物生活の、ゆるーい目指し方」
こんなテーマで話していきます。
どうも、少ない持ち物で生活することを心がけている自称ミニマリストです。
少ない持ち物生活はホントに楽なんですよーという話は、こちらの記事でも紹介しています:ミニマリスト生活をするメリットをゆるーく紹介【実体験】
#不要なモノをなんでわざわざ持っているんだ?という話をつらつら書いた
本記事では、「少ない持ち物で生活する方がお得だよね」という前提のもと、快適に暮らすための手順について実体験ベースで勝手に語ります。
長続きしやすい&細かいコツの紹介ナッシングの精神で説明していきますね。
結論、これだけ。
① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
この流れを深掘りしていきます。
自己紹介
持ち物の多さに疲れ、ミニマリスト的な生活を目指し始めた。
もう5年ほど、少ない持ち物で生活している。
とりあえず、余計な物に邪魔されずに生きたいと日々思っている。
目次
ミニマリスト生活のゆるーい目指し方

冒頭でも紹介しましたが、
「不要なモノを手放しきって、少ない持ち物生活をしてみたい」と思ったときの手順は以下の通り。
・自分にとって必要な物を整理する
・それ以外の持ち物を手放す
・①②を繰り返す
正直、この流れは片付け系の本にもよく書かれている。
ただ、結論がシンプルすぎて、それらの本の序盤の方に書かれているだけ。
あとは本としてのボリュームアップのための細かい片づけのコツの話が増え、上記のような本質の話が埋もれているのかなーと思ったりしています。
細かいコツは試行錯誤で自然と身につくので、まずはこの流れを徹底するだけで十分だったりする。
それぞれ補足させてください。
① 自分にとって必要な物を整理する
① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
まずは、この中の「① 自分にとって必要な物を整理する」について!
不要な物を手放す前に、必要な物を整理しておくことで手放しすぎ・残しすぎを防げるんですね。
経験上、以下の2ステップでだいたい整理できます。
1. カテゴリ別に今の生活から必要なモノ・数を決定する
2. 持っている物の優先順位を決める
少しだけ補足させてください。
カテゴリ別に今の生活から必要なモノ・数を決定する

必要な物はカテゴリ別に整理するのがオススメ。
カテゴリとは「Tシャツ」「靴下」「食器」など。
細かさはお好みで。
カテゴリ分けのメリット
・強制力が働く
⇒最初にそのカテゴリに関わるモノ全部リビングに集めれば、邪魔になって整理せざるを得ないよね
・必要な数を考えやすい
⇒カテゴリ毎なら、1点集中で必要なモノを考えやすい。
・持っている量に気づける
⇒自分の持っている物の量が多いことに気付いて、モチベーションUPに繋がる。
こんな感じでカテゴリごとに手放すものを考えていくことをオススメする。
今の生活を基準に考える
「カテゴリ別」を踏まえた上で、
今の生活を基に、必要なモノ・数を決定する方法の話に戻りますね。
必要な物は「今の生活」を基準に考えるのが大事。
過去や未来を基準にすると、不要な物まで残してしまいがち。
例:「Tシャツ」
・洗濯頻度:2日に1回
・使用頻度:毎日
⇒予備込みで4枚でOK

例:「文房具」
・ハサミ:必要。1部屋に1個でOK
・ノリ:1年使っていない → 不要
・ボールペン:、、(文房具は多いのでこのへんで割愛)

こんな感じで、今の生活を基準に「必要かどうか」「何個必要か」を考えていくと整理しやすいよ。
大事なことは必要なモノは「今の生活」を基準に考えること。
過去や未来を考えて、必要なモノや数に制限をかけることは非常にもったいない。
※「お気に入りのコートが2着あるから、コートは2着残そう」
このように持っている物から逆算すると、必要以上に残してしまいがち。
目的は「快適に暮らすこと」
そのためにも、今の生活を基準に必要な物を選ぶことがオススメ。
優先順位を決める
ここまでで、カテゴリ別に「残すモノ」と「残す数」がだいたい決まったはず。
あとは、今持っている物の中で優先順位を決めて、上位のものを残すだけ。
優先順位を決める基準は人それぞれ。
例えば:
・デザイン性
・機能性
・思い出補正
このあたりは、お任せ。
取捨選択が難しいと感じる場合は、無理に決めなくても大丈夫。
優先順位が決めきれないモノは、いったん後回しでOK。
他のカテゴリで選別を進めるうちに、自然と判断しやすくなっていくので。
僕自身も、最初はお気に入りのモノに優先順位をつけるのが難しかったですが、手放すことに慣れてくると、そこまで苦にはなりませんでした。
慣れは偉大。
慣れるためにもこれからの自分の生活に必要なモノについて悩む時間は決して無駄ではなく、むしろ良い時間だと思っています。
ぜひ一度、向き合ってみてください。
② それ以外の持ち物を手放す

① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
「① 自分にとって必要な物を整理する」の説明がちょっと長くなってしまいましたが、次は選定した「必要なモノ以外」をすべて手放そう。
手放す方法は世の中にたくさんあります。
代表的なものは「捨てる」「売る」など。
一見、「売る」方が得するように思えるかもしれませんが、売ることにこだわりすぎると、売れないモノが残り続けてしまい、結局、不要なモノが家に居座り続けることになるなんてことはよくあること。
最悪の場合、選定した「不要なモノ」が元の場所に戻ってしまうことも、、
そのため、手放し方についてもある程度理解しておくのがおすすめ。
ここでは僕の経験をもとに、代表的な手放し方の特徴を整理してみます。
あくまで僕の経験にはなりますが、各手放し方の良さ・悪さについてシェアしたいと思います。
・捨てる
・人にあげる
・フリマサービス
・宅配買い取り
・店頭買い取り
それぞれについて、金額・時間・手間・対応範囲の観点で見ていきます。
※金額:得られる収益/時間:必要な作業時間/手間:作業の煩雑さ/対応範囲:対象となるモノ
1.捨てる
まず、王道の持ち物の手放し方である「捨てる」について。
・金額:0円
・時間:手放すモノをまとめる時間・リサイクルセンターに行く時間(2,3往復)
・手間:手放すモノをまとめる時間・リサイクルセンターに行く時間(2,3往復)
・対応範囲:全てのモノ
※金額:得られる収益/時間:必要な作業時間/手間:作業の煩雑さ/対応範囲:対象となるモノ

お金にはならないですが、思考停止で手放せるので一番ラク。
ゴミの日に出せるモノは簡単ですが、大型のモノはリサイクルセンターへ。
僕の場合、2〜3往復した記憶が、、量によってはそれなりに大変。
でも、思考停止で捨てることができるため、なんだかんだ1番楽な持ち物の手放し方。
2.人にあげる
次に、「人にあげる」手放し方について。
・金額:0円
・時間:かからない
・手間:かからない
・対応範囲:人が欲しがるモノ
※金額:得られる収益/時間:必要な作業時間/手間:作業の煩雑さ/対応範囲:対象となるモノ
もちろん、人にあげるだけなので、お金にはなりません。
僕の場合、友人を家に招いて「欲しいものがあれば持っていって〜」というスタイルでやっていました。
押し売りはNG。相手の判断に任せるのがポイント。
意外と嬉しいポイントが、友人が自分のモノを使ってくれること。
感謝されるし、気持ちよく手放せる。

3.フリマサービス

ここからは、「売る」ことについての話になります。
「売る」といっても、売り方によって特徴は大きく変わってくるので、分けて書きますね。
まずは、「フリマサービス」による手放し方について。
・金額:売れれば高い
・時間:撮影/梱包/発想/スマホの確認など
・手間:出品状況の管理が必要なため、そこそこ大変
・対応範囲:売れるモノ
※金額:得られる収益/時間:必要な作業時間/手間:作業の煩雑さ/対応範囲:対象となるモノ
フリマサービスとは、個人間のやりとりで売る方法。
例えば、こんなサービスがある。
・メルカリ
・ラクマ
・ジモティ
※ジモティは利益を得ることはできないため、厳密には違うかも
個人間のやり取りなので、売れれば店頭より高く売れる可能性あり。
ただし、売れなければ0円。
ただねー
僕も何度か使いましたが、正直そこそこ面倒でした。
・汚れや傷の確認
・写真撮影
・発送準備
・購入者とのやり取り
悪い評価がつくと売れにくくなるなど、意外と気を遣う必要がある、、
送料はこちらが負担しないと売れづらいのも注意点。
安いモノは利益が出にくいので、ある程度値段がつくモノを数点売るのが良さそう。
4.宅配買い取り
次に、「宅配買い取り」について。
・金額:安い
・時間:梱包と手続きに使う時間くらい
・手間:梱包と手続きの手間
・対応範囲:売れるモノ(基本何でも)
※金額:得られる収益/時間:必要な作業時間/手間:作業の煩雑さ/対応範囲:対象となるモノ
宅配買い取りとは、自分で売りたいモノを段ボールに詰めて、配送するサービス。
自宅まで取りに来てくれるサービスもたくさんあります。
例えば、このようなサービス。
・アマゾンの宅配買い取りサービス(リコマース)
・ブックオフの宅配買い取りサービス

僕も使ったことがありますが、段ボールに詰めるだけなので手間は少なくて楽。
ただし、金額は期待しない方がいい、、
キャンセル時の手続きも少し面倒なので、最悪「全部手放す」くらいの気持ちで使うのが良いかも。
#もちろんゴミを送り付けることはNG
売るモノを店まで持ち運ぶ作業ができない方にはぴったりだと思います。
一気に多量のモノを売りたいときにはオススメ。
5.店頭買い取り
最後に、「店頭買い取り」について。
・金額:安い(返品可能/交渉可能)
・時間:店に持っていくことに時間が必要
・手間:店に持っていく必要あり
・対応範囲:売れるモノ(基本何でも)
※金額:手放すことで得ることができる金額 / 時間:手放すために必要な時間 / 労力:手放すために必要な労力 / 対応範囲:手放すことが可能なモノ
店頭買い取りとは、ご存じかと思いますが、
自分で売るモノを店に持って行って、売ることですね。
ブックオフで本を売ることと同じ。
移動手段がある人向け。
返品や値段交渉がしやすいのがメリットかな。
やってみたところ、持ち込んで待つだけだったので、かなり楽でした。
ただし、車などがないと少し面倒かもしれません。
以上、ここまで「手放す手段」について僕の経験談を基に書いてみました。
少なくとも、この記事では僕の感覚で書いているので、実際に色んな手放し方をやってみて、感覚を掴むことをオススメします!
他にも、良い手放し方があれば逆に教えて欲しいです、、
③ ①②を繰り返す

① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
最後のステップ「③ ①②を繰り返す」について簡潔に説明しますね。
「②で断捨離終了!これで少ない持ち物生活だ!」
とは、ほとんどの場合なりません。
不必要なモノを一度で完全に捨てきるのは難しいんですよねー
断捨離に慣れていないと、「必要だと勘違いしているモノ」を残してしまっているんですよ。
最初は手探り状態。
①②の作業を何度も繰り返すことで、本当に必要なモノだけが残っていくと思ってて。
もうここは繰り返すしかないかと。
僕自身も、3年ほどかけてようやく「これ以上は手放せないな」というラインに到達した気がします。
根気のいる作業かもしれませんが、
最初の数回で少ない持ち物の快適さを実感できれば、意外とスムーズに進みますよ。
1回の断捨離ですべてを終わらせようとする必要はナッシング。
気楽にいきましょう。
断捨離はシンプルだけど、時間のかかる作業です。
応援しています!
なるべく残す物から考える

① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
この流れについて、少し補足させてください。
まあぶっちゃけこのやり方だと、いきなり「捨てる作業」に入れないので、じれったく感じるかもしれません。
それでも、まずは落ち着いて「残すモノ」を選ぶことをオススメします!
いきなり捨てるモノを探すのも、短期的には効果があるとは思う。
ただ、長期的に快適な生活を目指すなら、先に残すモノを選ぶ方が効率的。
理由はこんな感じ。
・残すモノより捨てるモノの方が圧倒的に多い
・必要なモノだけを残すためには、残す基準が必要
僕自身も、家の中に想像以上に不要なモノがあることに驚きました。
だからこそ、まず残すモノを選定して、それ以外を手放す方がスムーズ。
また、少ない持ち物で快適に暮らすには「自分にとって必要なモノ」だけを持つことが重要。
多すぎても少なすぎても、快適さからは遠ざかります。
手放しすぎると生活に支障が出るし、残しすぎると余計なモノで損をする。
だからこそ、「自分にとって必要なモノ」を選ぶことが大切なんですよね。
この作業は時間がかかりますが、
自分の生活を見直すきっかけにもなるし、地味に楽しかったりする。
ここがファーストステップです。
焦らず、じっくり取り組んでみてください。
手放しやすいカテゴリから始める
もういっしょ補足。
「どんなモノから自分にとって必要なモノを決定するべきか」

これは多くの片づけ本にも書かれていることですが、
まずは「手放しやすいカテゴリ」から始めるのがオススメ。
理由はシンプルで、手放すハードルが低い方がモチベーションが上がるから。
部屋の掃除・片付け・必要なモノの選定など、整理整頓に関わる作業は基本的に面倒くさいもの。
このときに重要なのは「モチベーション」
これがないと継続は無理。
必要なモノを選定したあと、すぐに手放せると、少ない持ち物生活の良さを少しでも実感できて、モチベーションUPになるんですよね。
逆に、「手放すの面倒くさいな、、」という思考が入ると、やる気が下がる。
これでは継続は難しい。
例えば、「Tシャツ」「文房具」「靴下」などは、毎週のゴミ捨てで対応できるモノが多いので、手放しやすいカテゴリ。
こういったカテゴリから始めることで、継続しやすくなると思っています。
また、「普段よく使っているモノのカテゴリ」から選ぶという方法を推す人もいます。
必要かどうかの判断がしやすいからですね。
このあたりはもう好みの問題。
自分に合うやり方が一番かな。
僕の場合は「手放しやすい」カテゴリから始めるのが合っていました。
まとめ
この記事では、余計なモノを手放しきった少ない持ち物生活のゆるーい目指し方について紹介しました。
① 自分にとって必要な物を整理する
② それ以外の持ち物を手放す
③ ①②を繰り返す
とにかく、「選定 → 手放す」作業を繰り返してみてください。
少しずつ、自分にとって必要なモノが整理されていく感覚が楽しいので、地味にオススメ。
気楽に、ゆるーく続けていきましょう。
以上、
最後まで読んでいただきありがとうございます。
下記の記事では、ミニマリスト生活の良さについてザックリ説明しています。よかったら読んでみてください。